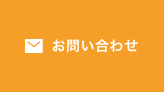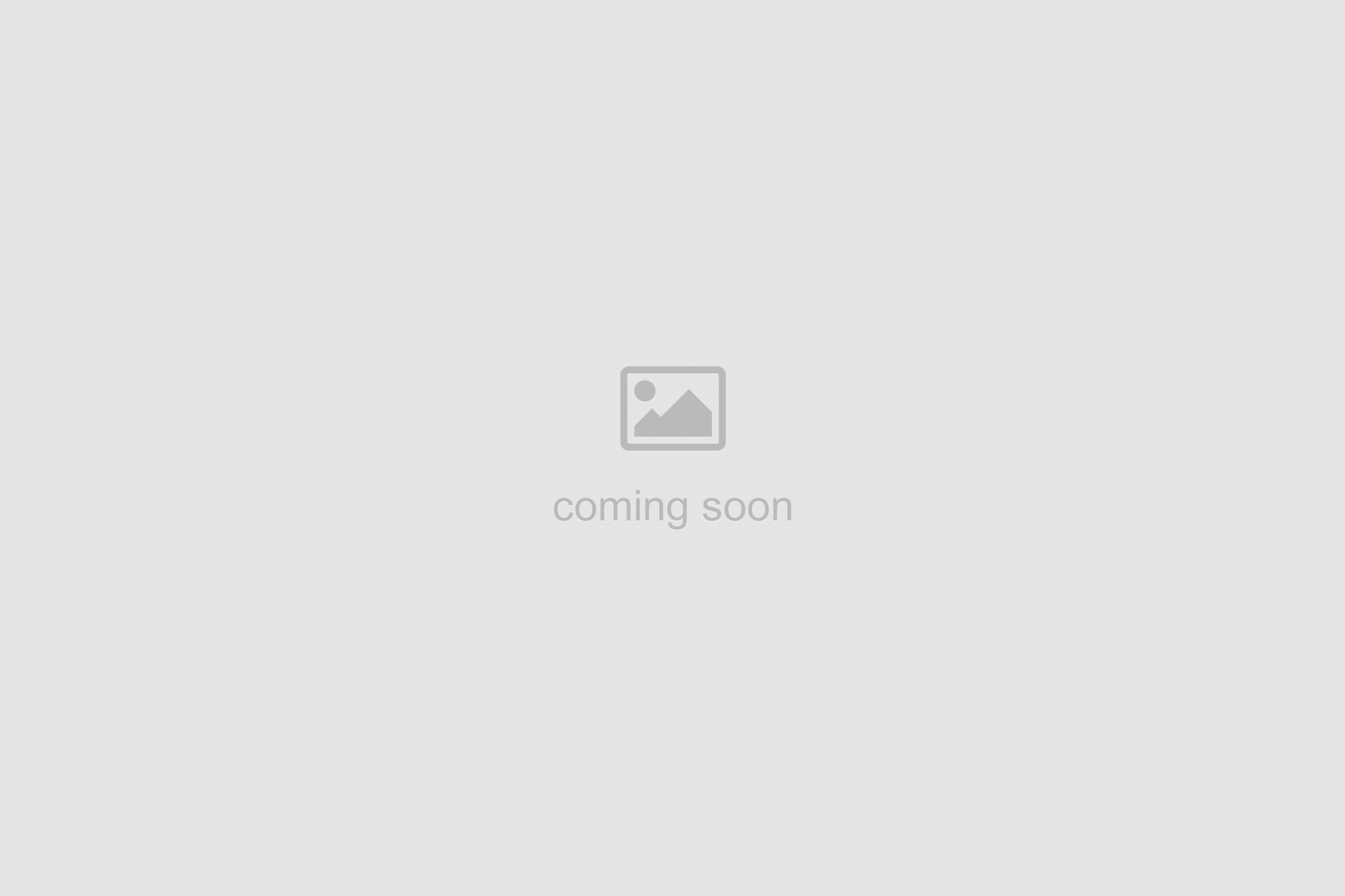令和6年4月
2024-04-16
大漁祈願祭
第89回の大漁祈願祭が三嶋大社で開催されました。
かつての漁業、特にエンジンがない漁船を使っていたころは
急な天候変更に対応できず、海難事故が多発しました。
このため、神社仏閣は漁師にとって大事な存在。
多額の献金していました。
その名残で、各地で盛大に祈願祭が行われてます。
ただ、今では海の資源が有限であることが分かっています。
かつての漁業、特にエンジンがない漁船を使っていたころは
急な天候変更に対応できず、海難事故が多発しました。
このため、神社仏閣は漁師にとって大事な存在。
多額の献金していました。
その名残で、各地で盛大に祈願祭が行われてます。
ただ、今では海の資源が有限であることが分かっています。
海難事故は技術の進歩で激減しました。
祈っていても資源は増えません。
神頼みでは、山積する漁業の課題が解決しないことは漁師も知っています。
50年前に観た映画タイタニックでは、
「神に祈るより、助かるために行動しろ」
と神父が導き、行動を起こした人は助かりました。
今、漁業者はどんな行動を起こすべきでしょうか。
誰のこと?
静岡県知事が辞任に追い込まれた発言。
「毎日毎日、野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、
あるいはモノを作ったりとかということと違って、
基本的にみなさんは頭脳・知性の高い方。」
・・・これって、一次産業、二次産業、三次産業を卑下しています。
じゃあ、該当しないのは
県庁職員などの公務員
大学教授などの学者(研究者)
くらいになってしまいます。
あら不思議、川勝さんはどちらも当てはまっていますよ!
さて、我々の業界ですが高学歴の人は少ないですが
頭脳・知性の高い人はいます。
そして、バカとしか思えない研究者もたくさんいます。
大型漁船の漁労長なんて、漁獲量の実績で地位を維持しています。
常に結果を出している点では、研究者よりすごいんじゃないかな。
「毎日毎日、野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、
あるいはモノを作ったりとかということと違って、
基本的にみなさんは頭脳・知性の高い方。」
・・・これって、一次産業、二次産業、三次産業を卑下しています。
じゃあ、該当しないのは
県庁職員などの公務員
大学教授などの学者(研究者)
くらいになってしまいます。
あら不思議、川勝さんはどちらも当てはまっていますよ!
さて、我々の業界ですが高学歴の人は少ないですが
頭脳・知性の高い人はいます。
そして、バカとしか思えない研究者もたくさんいます。
大型漁船の漁労長なんて、漁獲量の実績で地位を維持しています。
常に結果を出している点では、研究者よりすごいんじゃないかな。
令和6年3月
2024-03-29
サンドイッチマンすごいな
気仙沼視察のとき。
バス移動が多かったのですが、超ベテランのガイドさんが同乗してくれました。
そして話の大半が
「サンドイッチマンがここでロケした」
など。
気仙沼とか宮城の歴史や地理の話は?
詳しいでしょ?
サンドイッチマンの宮城県への貢献は凄いと思いますが、
静岡からの視察者に、その話題ばかりされても...
ところで、気仙沼は全国で13しかない特別第3種漁港で、特別大きな拠点漁港。
静岡県の場合は焼津が特3漁港です。
でも大きな違いを感じました。
静岡県では焼津に一極集中でダントツの水揚です。
しかし、気仙沼は近くに大船渡や石巻などの大規模水揚げ港がいくつもあります。
他にも水揚げ魚種の多さなど、いろいろな違いを感じました。
さて、来週から新年度となります。
さっそく、補助事業の募集を始める予定です。
漁協へはファクスで直接通知するほか、このホームページでもご案内します。
バス移動が多かったのですが、超ベテランのガイドさんが同乗してくれました。
そして話の大半が
「サンドイッチマンがここでロケした」
など。
気仙沼とか宮城の歴史や地理の話は?
詳しいでしょ?
サンドイッチマンの宮城県への貢献は凄いと思いますが、
静岡からの視察者に、その話題ばかりされても...
ところで、気仙沼は全国で13しかない特別第3種漁港で、特別大きな拠点漁港。
静岡県の場合は焼津が特3漁港です。
でも大きな違いを感じました。
静岡県では焼津に一極集中でダントツの水揚です。
しかし、気仙沼は近くに大船渡や石巻などの大規模水揚げ港がいくつもあります。
他にも水揚げ魚種の多さなど、いろいろな違いを感じました。
さて、来週から新年度となります。
さっそく、補助事業の募集を始める予定です。
漁協へはファクスで直接通知するほか、このホームページでもご案内します。
気仙沼漁港
先週、気仙沼漁港に行ってきました。
30年ぶりでしたが、特徴的な市場の屋根は見覚えがありました。
震災で大きな被害があった気仙沼ですが、魚市場はそのまま残ったようです。
でも、地番沈下により屋根が下がりトラックが入ってこられない場所がありました。
さて、気仙沼はサメの水揚が多いことでも有名です。
マグロはえ縄漁船が多く、もともとはマグロ漁で混獲したサメが水揚げされていました。
本県の場合、サメと言えば食害です。
キンメダイを釣り上げるとき、食い荒らすので、サメが来ると、漁になりません。
しかし、サメを捕獲すると保護団体からいろいろあります。
気仙沼では保護団体からのクレームや妨害はないそうです。
どうしてでしょうね?
30年ぶりでしたが、特徴的な市場の屋根は見覚えがありました。
震災で大きな被害があった気仙沼ですが、魚市場はそのまま残ったようです。
でも、地番沈下により屋根が下がりトラックが入ってこられない場所がありました。
さて、気仙沼はサメの水揚が多いことでも有名です。
マグロはえ縄漁船が多く、もともとはマグロ漁で混獲したサメが水揚げされていました。
本県の場合、サメと言えば食害です。
キンメダイを釣り上げるとき、食い荒らすので、サメが来ると、漁になりません。
しかし、サメを捕獲すると保護団体からいろいろあります。
気仙沼では保護団体からのクレームや妨害はないそうです。
どうしてでしょうね?
原因は予想外
パソコントラブルの話です。
自宅で使っているパソコンは、起動ドライブをSSDと言うメモリー型に換えているので、1分ほどで起動します。
が、この数日、激遅になりました。
さっそく原因をググるといろいろありした。
SSDの劣化、Windowsの不具合、メモリ不足、ウイルス感染・・・
などなど。
対策を一通りやりましたが、改善なし。
何度も再起動して気がつきました。
Windowsが起動した後、画面にアイコンが並び、操作ができるまでが長い!
普通は数秒です。
で調べると、この間に起動ドライブ以外をずーとアクセスしています。
ちょっと苦労して、そのドライブをフォーマットしたところ解決!
起動ドライブ問題ないじゃん。
これって、パソコンに詳しい人ならすぐに気づいたんですかね?
以上、どうでも良い話でした。
自宅で使っているパソコンは、起動ドライブをSSDと言うメモリー型に換えているので、1分ほどで起動します。
が、この数日、激遅になりました。
さっそく原因をググるといろいろありした。
SSDの劣化、Windowsの不具合、メモリ不足、ウイルス感染・・・
などなど。
対策を一通りやりましたが、改善なし。
何度も再起動して気がつきました。
Windowsが起動した後、画面にアイコンが並び、操作ができるまでが長い!
普通は数秒です。
で調べると、この間に起動ドライブ以外をずーとアクセスしています。
ちょっと苦労して、そのドライブをフォーマットしたところ解決!
起動ドライブ問題ないじゃん。
これって、パソコンに詳しい人ならすぐに気づいたんですかね?
以上、どうでも良い話でした。
令和6年2月
2024-02-28
進学とは??
高校や大学への進学率が増えると、進学が当たり前になって、目的を見失っているように思います。
ところで、漁師になるための学校「静岡県立漁業高等学園」があります。
定員が30人、1年で卒業の小さい学校です。
中学卒業者から30歳までの様々な生徒が全国から集います。
大半の生徒は中学まで勉強をほどんどしていません。
それが入学後は「海技士資格」などの勉強に取り組むようになります。
卒業式には目つきのしっかりした人に育ちます。
漁業と言う厳しい現場でも高い定着率を誇ります。
学歴と言う看板は、今や価値がありません。
学歴は看板でなく、技能や生きていく力を身に着けるものと視点を変えてはいかがでしょうか?
何年もかけて高校、専門学校、大学に行くんです。
有益に使ってほしいと思います。
ところで、漁師になるための学校「静岡県立漁業高等学園」があります。
定員が30人、1年で卒業の小さい学校です。
中学卒業者から30歳までの様々な生徒が全国から集います。
大半の生徒は中学まで勉強をほどんどしていません。
それが入学後は「海技士資格」などの勉強に取り組むようになります。
卒業式には目つきのしっかりした人に育ちます。
漁業と言う厳しい現場でも高い定着率を誇ります。
学歴と言う看板は、今や価値がありません。
学歴は看板でなく、技能や生きていく力を身に着けるものと視点を変えてはいかがでしょうか?
何年もかけて高校、専門学校、大学に行くんです。
有益に使ってほしいと思います。
工業高校
ある学校で生徒の学力が上がり、大学進学率が向上していることを自慢していました。
大学進学者が多いのなら、普通科で良いのでは??
国立大学では以前から「実業高校枠」があって、推薦入学できます。
この推薦入学は普通科では使えません。
普通科からは進学できない大学に、実業高校なら同じ学力でも合格できるかもしれません。
ただし、大学へ進学できれば終わりではありません。
推薦入学の人は一般入試の学生より学力は低いので、入学してから苦労します。
そして退学する人も多くなります。
まあ、中には就職するつもりで工業高校に進学し、途中で大学進学に変更する人もいるでしょう。
それは少数です。
続いて水産高校
同じく進路指導担当者の話
「本校は海員(船乗り)の養成校で、商船などに就職することを目指してる。
危ない漁船に乗せる必要はない」
これ本当ですよ。
漁業を蔑視する感がありありです。
確かに、水産高校は海員養成校としても位置付けられてはいます。
でも海技学校や商船高専とは違います。
なんで水産や漁業の授業があるのか?って話ですよ。
現在の漁協の組合長は水産高校出身者がたくさんいます。
50年くらい前だと、漁村から高校進学する人は少なく、地域の名家が水産高校に行けたのです。
名家は大袈裟化も知れませんが、裕福な家庭の出身です。
聞けば、当時の水産高校は漁業経験のある補助教員がいて、現場の作業も教えてくれたそうです。
今や水産高校だと人気がないので海洋高校と名前を変えている場合も。
あるいは統合で総合学科になったりしています。
こんな状況でも、外向きに業界に貢献しているアピールも必要なようで、
漁業会社へ事務職で入った女子生徒を「漁業に就職」としてカウントするなど、
涙ぐましい?こともしています。
進学は何のために?
2月11日に神奈川県にある日本さかな専門学校の学園祭があるそうです。
なぜ、この時期に???
入試真っ最中ですよ。
もしかしたら定員割れで、学生集めでしょうか?
ところで以前、高校を巡回して、進路指導担当者と面談をしていました。
そこで感じた違和感です。
まずは農業高校。
「農家のほとんどは兼業で、農家の子供でも卒業後に農業はしない。
だから在学中は『いかに楽しく過ごせるか』を考えている」
それで良いの?何のための農業高校?
しかし、実態として高校進学は中学の成績で管内の公立高校に振り分けられます。
農業のことを学びたくて、農業高校に進学する人がどれだけいるか。
また、「座学よりも農業実習の方が楽しそう」だから、あえて農業高校を選ぶこともあります。
高校側も定員割れが多く、とにかく生徒を増やしたい思惑があります。
加えて、高学歴化で大学等に進学する人が増えました。
99%以上が高校進学、その7割が大学や専門学校へ進学します。
高校は経過するだけです。
就職に重きをおく必要が減りました。
入学する側も、学校側も、どっちもどっちです。
(つづく)
なぜ、この時期に???
入試真っ最中ですよ。
もしかしたら定員割れで、学生集めでしょうか?
ところで以前、高校を巡回して、進路指導担当者と面談をしていました。
そこで感じた違和感です。
まずは農業高校。
「農家のほとんどは兼業で、農家の子供でも卒業後に農業はしない。
だから在学中は『いかに楽しく過ごせるか』を考えている」
それで良いの?何のための農業高校?
しかし、実態として高校進学は中学の成績で管内の公立高校に振り分けられます。
農業のことを学びたくて、農業高校に進学する人がどれだけいるか。
また、「座学よりも農業実習の方が楽しそう」だから、あえて農業高校を選ぶこともあります。
高校側も定員割れが多く、とにかく生徒を増やしたい思惑があります。
加えて、高学歴化で大学等に進学する人が増えました。
99%以上が高校進学、その7割が大学や専門学校へ進学します。
高校は経過するだけです。
就職に重きをおく必要が減りました。
入学する側も、学校側も、どっちもどっちです。
(つづく)
例えばこんな人
知人に、ある市役所のOBがいます。
定年後、市の職員に再任用されましたが、それもこの3月で終ります。
その人は水産系大学の出身なんですけど、市役所では水産以外の部署に配置されることが多かったんです。
そのためか、今後は業界に貢献したいと言ってます。
低賃金のアルバイトでも良いそうです。
市の幹部職員だったので、優秀な人です。
水産系の出身者は、市の職員でも水産系の業務にずっといることが多いのですが、こんな人もいます。
水産関係にどっぷりしていなかったメリットは結構あります。
他分野の見識があるし、業界外の伝手もある。
例えば、漁協の組合長とは言いませんが、ブレーンとして活躍してくれそうです。
前のブログに書きましたが、実際にこんな人材がいるんです。
定年後、市の職員に再任用されましたが、それもこの3月で終ります。
その人は水産系大学の出身なんですけど、市役所では水産以外の部署に配置されることが多かったんです。
そのためか、今後は業界に貢献したいと言ってます。
低賃金のアルバイトでも良いそうです。
市の幹部職員だったので、優秀な人です。
水産系の出身者は、市の職員でも水産系の業務にずっといることが多いのですが、こんな人もいます。
水産関係にどっぷりしていなかったメリットは結構あります。
他分野の見識があるし、業界外の伝手もある。
例えば、漁協の組合長とは言いませんが、ブレーンとして活躍してくれそうです。
前のブログに書きましたが、実際にこんな人材がいるんです。
令和6年1月
2024-01-31
人材の確保
どこの業界も高齢化して、若年者の労働力は不足しています。
さらに顕著なのが漁業の世界。
・・・ではあるんですが、漁協などの事務方なら話は別です。
今話題の「海業」などを進める上で、適した人材がいるかも。
それは役所などを退職した人たち。
学力もあるし、水産関連の知識もあるから即戦力。
加えて、新卒を雇うより安上がり。
言うことなしじゃないですか?
経営的なことなら、金融機関の退職者もいいですね。
漁業は外部からの参入が難しいですが、逆に自分から外部の人材活用を考えても良い気がします。
さらに顕著なのが漁業の世界。
・・・ではあるんですが、漁協などの事務方なら話は別です。
今話題の「海業」などを進める上で、適した人材がいるかも。
それは役所などを退職した人たち。
学力もあるし、水産関連の知識もあるから即戦力。
加えて、新卒を雇うより安上がり。
言うことなしじゃないですか?
経営的なことなら、金融機関の退職者もいいですね。
漁業は外部からの参入が難しいですが、逆に自分から外部の人材活用を考えても良い気がします。
大間のマグロの功罪
豊洲市場で行われたマグロの初競りは青森県大間産のクロマグロが過去4番目に高い1億1424万円で競り落とされました。
昨年の約3倍で、1億円を超えたのは新型コロナウイルス流行前の2020年以来、4年ぶり。
業界にとって魚が高く売れるのは良いことです。
しかし、この尋常ではない金額は素直に喜べません。
その理由です。
1 大間のマグロは特別ではない
大間に水揚げされるマグロは津軽海峡で漁獲されたものです。
津軽海峡では北海道の漁師も操業しています。
漁獲後の処理が違うかもしれませんが、同じマグロです。
2 一番マグロ以外の魚価への影響
大間産以外のマグロについても同じですが、1番マグロに資金がつぎ込まれる弊害です。
仲買人が魚を仕入れる資金が1番マグロに偏るのは、それ以外の魚に資金が回らないことになります。
3 マグロ漁の多くは・・・
テレビで大間のマグロ漁師が注目されるのは悪いことではありません。
しかし、漁業を知らない多くの視聴者は、これがマグロ漁の世界と思ってしまいます。
実際には、販売されるマグロの多くは遠洋で漁獲されたものです。
遠洋漁船が半年から2年も出漁し、はえ縄で漁獲し、1日の操業時間は20時間にもなります。
ところで、山梨県の方は「魚と言えばマグロ」だそうです。
私は漁村の生まれなので、アジやサバの方がマグロよりも好きです。
それもあって、初セリでの1番マグロの金額には、毎年、複雑な思いです。
漁業と被災地への物流
元旦から大きな災害が発生しました。
道路や港が被災して、支援物資の供給が進まないようです。
こんなときに活用できるのが小型漁船です。
漁船でも荷物は積めます。
小さいので、大きな船舶が港に入れないときでも、荷揚げができます。
海から被災地が離れていると、そこでの物流が問題ですが...
なにはともあれ、少しでも早く、物資が届くことを祈ります。
道路や港が被災して、支援物資の供給が進まないようです。
こんなときに活用できるのが小型漁船です。
漁船でも荷物は積めます。
小さいので、大きな船舶が港に入れないときでも、荷揚げができます。
海から被災地が離れていると、そこでの物流が問題ですが...
なにはともあれ、少しでも早く、物資が届くことを祈ります。
令和5年12月
2023-12-27
明日の水産業界に必要なのは
今年も業界の縮小に歯止めがかかりませんでした。
水揚げ減少、諸物価高騰など悪いことはたくさんあります。
その中で一番の懸念は水産に関わる人が減っていることです。
県内でも、特に伊豆では主要産業が漁業である地域がまだまだあります。
そんな地域で漁業者の減少は地域の衰退となります。
水産加工業、仲買人も跡継ぎがおらず、減る一方。
減り方が漁師より深刻な場合もあります。
この傾向が、一変することは期待薄です。
ところで、太平洋戦争のあと日本国内には250社以上のオートバイメーカーがあったそうです。
その中で生き残ったのがホンダ(本田技研工業)ほか4社です。
ホンダの創設者である本田宗一郎さんは余りにも有名です。
しかし、会社の経営を行ったのは副社長の藤沢武夫さん。
https://inging.jp/column-consultant/丸正自動車製造の倒産理由から見える正しい経営/
に、このように書かれています。
「技術者の社長は、たいてい財務は苦手です。財務の基本は、「入るを量りて出ずるを為す」です。収入を計算して、それに見合った支出を行うことです。財務部門でのミスは、野球で言うところの外野のエラーのようなもので、必ず痛手を被ります。
会社が大きくなると、経営判断の誤りが、大きな損失につながるため、分野ごとに能力のある幹部を集め、経営の全方位を固める必要があります。藤沢武夫は、本田宗一郎が苦手とするところをすべて担い、開発部門以外の人選や人材育成も行いました。」
この「技術者」を「漁師」に置き換えるとどうでしょうか?
せめて漁協にでも、漁師が苦手とすることを担ってくれる人材がいれば...
でもホンダが生き残ったのは、本田宗一郎さんが藤沢武夫さんを受け入れたからです。
水産業界にも、この判断が求められている気がします。
水揚げ減少、諸物価高騰など悪いことはたくさんあります。
その中で一番の懸念は水産に関わる人が減っていることです。
県内でも、特に伊豆では主要産業が漁業である地域がまだまだあります。
そんな地域で漁業者の減少は地域の衰退となります。
水産加工業、仲買人も跡継ぎがおらず、減る一方。
減り方が漁師より深刻な場合もあります。
この傾向が、一変することは期待薄です。
ところで、太平洋戦争のあと日本国内には250社以上のオートバイメーカーがあったそうです。
その中で生き残ったのがホンダ(本田技研工業)ほか4社です。
ホンダの創設者である本田宗一郎さんは余りにも有名です。
しかし、会社の経営を行ったのは副社長の藤沢武夫さん。
https://inging.jp/column-consultant/丸正自動車製造の倒産理由から見える正しい経営/
に、このように書かれています。
「技術者の社長は、たいてい財務は苦手です。財務の基本は、「入るを量りて出ずるを為す」です。収入を計算して、それに見合った支出を行うことです。財務部門でのミスは、野球で言うところの外野のエラーのようなもので、必ず痛手を被ります。
会社が大きくなると、経営判断の誤りが、大きな損失につながるため、分野ごとに能力のある幹部を集め、経営の全方位を固める必要があります。藤沢武夫は、本田宗一郎が苦手とするところをすべて担い、開発部門以外の人選や人材育成も行いました。」
この「技術者」を「漁師」に置き換えるとどうでしょうか?
せめて漁協にでも、漁師が苦手とすることを担ってくれる人材がいれば...
でもホンダが生き残ったのは、本田宗一郎さんが藤沢武夫さんを受け入れたからです。
水産業界にも、この判断が求められている気がします。
それでは、良いお年を
もう12月・・・
なんだかんだで、今年も残り少なくなりました。
今年はマスク着用者が減り、生活も元に戻ってきましたね。
ところで、先日、神奈川県の三浦市にある城ヶ島に行ってきました。
島と言っても橋で渡れるし、長さも1.8キロしかありません。
夕方で風も冷たかったのですが、ウエディングドレス、タキシードのカップルがたくさん。
島のあちらこちらで写真撮影をしていました。
その関係では人気スポットになっているようです。
一般の人にとって、海と言うだけで大きな魅力があることを再認識しました。
これから発掘できる漁村や漁業の魅力はまだまだあると思いました。
来年は業界が上向きになることを願いします。
今年はマスク着用者が減り、生活も元に戻ってきましたね。
ところで、先日、神奈川県の三浦市にある城ヶ島に行ってきました。
島と言っても橋で渡れるし、長さも1.8キロしかありません。
夕方で風も冷たかったのですが、ウエディングドレス、タキシードのカップルがたくさん。
島のあちらこちらで写真撮影をしていました。
その関係では人気スポットになっているようです。
一般の人にとって、海と言うだけで大きな魅力があることを再認識しました。
これから発掘できる漁村や漁業の魅力はまだまだあると思いました。
来年は業界が上向きになることを願いします。
海鮮丼
旅行に行く楽しみの一つが食べることですよね。
せっかく海の近くや、漁業の盛んなところに行けば魚料理を食べたくなります。
お手頃なのが海鮮丼です。
でも、これって日本全国、どこにいっても似たようなものがでてきます。
例えば、伊豆でも
「マグロ、サーモン、イクラ、ホタテ、・・・・」
伊豆産がありません。
これなら、どこで食べても同じようなもん。
今日の水揚だけで作った海鮮丼!ってみたことありません。
日によって違うものになるのも旅の楽しみだと思うんですが。
せっかく海の近くや、漁業の盛んなところに行けば魚料理を食べたくなります。
お手頃なのが海鮮丼です。
でも、これって日本全国、どこにいっても似たようなものがでてきます。
例えば、伊豆でも
「マグロ、サーモン、イクラ、ホタテ、・・・・」
伊豆産がありません。
これなら、どこで食べても同じようなもん。
今日の水揚だけで作った海鮮丼!ってみたことありません。
日によって違うものになるのも旅の楽しみだと思うんですが。
当法人の債券運用
前回のブログで「魚は手間を掛けないと高く売れない」と言いましたが、偉そうに言っている場合ではありません。
当法人は財団法人であるため、資金の運用益を財源にしています。
ほとんどが国債、地方債などの債券です。
これが社債や株式なら、もっと多い収益が得られるかもしれません。
このため、安全な国債で運用していることを
「楽をしている」
と言われることもあります。
出捐いただいた資金なので、なるべく多くの運用益を得る必要があります。
リスクを負わないと、利益を多くできない・・・・
前述の漁師とあまり違わないのかも。
当法人は財団法人であるため、資金の運用益を財源にしています。
ほとんどが国債、地方債などの債券です。
これが社債や株式なら、もっと多い収益が得られるかもしれません。
このため、安全な国債で運用していることを
「楽をしている」
と言われることもあります。
出捐いただいた資金なので、なるべく多くの運用益を得る必要があります。
リスクを負わないと、利益を多くできない・・・・
前述の漁師とあまり違わないのかも。
令和5年11月
2023-11-09
サバの生食
静岡で水揚げされるサバにはアニサキスがいます。
アニサキスがいるサバを刺身で食べることはできません。
しかし、無害に処理する方法はあります。
一番かんたんなのが冷凍です。
天然魚のサケにも寄生虫がいるので、凍らせてから生食にします。
これはルイベとして知られています。
最近では冷凍せずとも、電気ショックで処理する方法も開発されています。
以前、サバを捕る漁業者から生食用として出荷する方法はないかと聞かれたことがあります。
しかし、冷凍するような手がかかる処理は嫌だと言います。
もし、手間もコストもかからずサバを生食にできれば素晴らしいです。
しかし、それは消費者にとってのこと。
この漁師の目的は生食用として高く売ること。
誰でも簡単にアニサキスの処理ができるなら、みんなやります。
それでも高く売れるでしょうか?
神経抜きなどの手がかかる処理も同じですが、手間がかかるから、処理した魚は高く売れます。
誰でも簡単にできるなら差別化になりません。
アニサキスがいるサバを刺身で食べることはできません。
しかし、無害に処理する方法はあります。
一番かんたんなのが冷凍です。
天然魚のサケにも寄生虫がいるので、凍らせてから生食にします。
これはルイベとして知られています。
最近では冷凍せずとも、電気ショックで処理する方法も開発されています。
以前、サバを捕る漁業者から生食用として出荷する方法はないかと聞かれたことがあります。
しかし、冷凍するような手がかかる処理は嫌だと言います。
もし、手間もコストもかからずサバを生食にできれば素晴らしいです。
しかし、それは消費者にとってのこと。
この漁師の目的は生食用として高く売ること。
誰でも簡単にアニサキスの処理ができるなら、みんなやります。
それでも高く売れるでしょうか?
神経抜きなどの手がかかる処理も同じですが、手間がかかるから、処理した魚は高く売れます。
誰でも簡単にできるなら差別化になりません。
漁協への支援
業界の意見を自民党や県議に話す機会があります。
とは言っても、私は同席するだけで話すのは業界の偉い人です。
そして、業界の厳しい状況を説明して、支援を要請します。
・・・ところで。
Youtubeに途上国への支援について、他国と日本との違いを説明する動画が多くあります。
例えば、アフリカへは現金や食料をばら撒くのではなく、住民が自立できるように技術支援するとか。
今の業界に対して、必要な支援はなにか。
漁業者も漁協職員も高齢化や人材難です。
自分で厳しい状況に適応できる力がありません。
漁村に常駐して、指導できる人材こそが必要な気がします。
当法人も、わずかばかりの補助金で漁協を支援しています。
でも、本当に必要なのは補助のいらない力のある業界になることです。
とは言っても、私は同席するだけで話すのは業界の偉い人です。
そして、業界の厳しい状況を説明して、支援を要請します。
・・・ところで。
Youtubeに途上国への支援について、他国と日本との違いを説明する動画が多くあります。
例えば、アフリカへは現金や食料をばら撒くのではなく、住民が自立できるように技術支援するとか。
今の業界に対して、必要な支援はなにか。
漁業者も漁協職員も高齢化や人材難です。
自分で厳しい状況に適応できる力がありません。
漁村に常駐して、指導できる人材こそが必要な気がします。
当法人も、わずかばかりの補助金で漁協を支援しています。
でも、本当に必要なのは補助のいらない力のある業界になることです。
令和5年10月
2023-10-31
富士山サーモン
先週、伊豆の網代で昼食をとりました。
刺身の盛り合わせがあり、うち一つが「富士山サーモン」とのことでした。
ほかにも下りカツオや、カキフライがあり、どれもおいしかったです。
網代は県内に2つある第3種漁港で、拠点漁港です。
とは言うものの、漁業は衰退。
カツオもサーモンもカキも、地元産ではありません。
それでも「富士山サーモン」は伊豆の山中で養殖されたものなので、地元産なのかな。
カツオやカキも県内産かもしれません。
伊豆に来る方の多くが海鮮を食べに来ます。
海鮮丼に必ずあるマグロは伊豆で捕れた可能性は限りなく少ないです。
メニューを固定しないで「水揚げされた魚だけを使う」ってすれば、良いと思います。
でも、人気はマグロやサーモンなんですよね。
マグロやサーモンを中心使うから、日本中どこいっても同じ魚が出てきます。
悲しい。
刺身の盛り合わせがあり、うち一つが「富士山サーモン」とのことでした。
ほかにも下りカツオや、カキフライがあり、どれもおいしかったです。
網代は県内に2つある第3種漁港で、拠点漁港です。
とは言うものの、漁業は衰退。
カツオもサーモンもカキも、地元産ではありません。
それでも「富士山サーモン」は伊豆の山中で養殖されたものなので、地元産なのかな。
カツオやカキも県内産かもしれません。
伊豆に来る方の多くが海鮮を食べに来ます。
海鮮丼に必ずあるマグロは伊豆で捕れた可能性は限りなく少ないです。
メニューを固定しないで「水揚げされた魚だけを使う」ってすれば、良いと思います。
でも、人気はマグロやサーモンなんですよね。
マグロやサーモンを中心使うから、日本中どこいっても同じ魚が出てきます。
悲しい。
令和5年9月
2023-09-22
キャンプと遠洋漁業
キャンプする人が増えています。
私にはキャンプの楽しさって、全然ピンときません。
自宅やホテルに泊まる方が快適なのに。
ところで遠洋漁業ですが、大変な世界です。
大儲けができたのは、昔の話。
長期間、船の上だし、勤務時間や休日がしっかり決まっていることもなく。
でも、この生活が好きな人もいます。
人混みから隔離されるのはキャンプと同じかもしれません。
また、昔より快適になってきています。
水がたくさん使えたり、船内WiFiがあったり。
キャンプが好きな人は、遠洋漁業にはまるかも知れません。
一泊二日で体験するってわけにはいきませんけど。
私にはキャンプの楽しさって、全然ピンときません。
自宅やホテルに泊まる方が快適なのに。
ところで遠洋漁業ですが、大変な世界です。
大儲けができたのは、昔の話。
長期間、船の上だし、勤務時間や休日がしっかり決まっていることもなく。
でも、この生活が好きな人もいます。
人混みから隔離されるのはキャンプと同じかもしれません。
また、昔より快適になってきています。
水がたくさん使えたり、船内WiFiがあったり。
キャンプが好きな人は、遠洋漁業にはまるかも知れません。
一泊二日で体験するってわけにはいきませんけど。
未だに新たな発見があるのは?
今年の放流事業では、いろいろな発見がありました。
私自体は3年目の仕事ですが、放流は何十年も前から行われてきたことです。
なんで、今になって・・・と外部の方は思うかもしれませんね。
これは放流事業が完成された技術によって行わていないことが原因です。
残念ながら、これが実態。
・・・なんですが、これが分かってもらえない。
別に本県だけの状況ではありませんが、
何十年も何やっているの
放流する意味あるの
なーんて、言われてしまいそうで積極的に言えない背景もあります。
私自体は3年目の仕事ですが、放流は何十年も前から行われてきたことです。
なんで、今になって・・・と外部の方は思うかもしれませんね。
これは放流事業が完成された技術によって行わていないことが原因です。
残念ながら、これが実態。
・・・なんですが、これが分かってもらえない。
別に本県だけの状況ではありませんが、
何十年も何やっているの
放流する意味あるの
なーんて、言われてしまいそうで積極的に言えない背景もあります。
令和5年8月
2023-08-25
中間育成の反省会 2
餌の量は研究所の担当者が魚の大きさや尾数から計算して、飼育担当者に指示します。
しかし1ヶ所だけ、養殖業者が世話をしている地区があり、そこでは飼育担当の養殖者が魚の様子を見て餌の量を決めます。
養殖業者がやっていた餌は他地区の2倍でした!
成長も全然違いました。
これが意味することは...
研究所の担当者は餌の量について、再吟味することになりました。
しかし1ヶ所だけ、養殖業者が世話をしている地区があり、そこでは飼育担当の養殖者が魚の様子を見て餌の量を決めます。
養殖業者がやっていた餌は他地区の2倍でした!
成長も全然違いました。
これが意味することは...
研究所の担当者は餌の量について、再吟味することになりました。
中間育成の反省会 1
マダイの放流が終わり、指導担当者の反省会を行いました。
指導担当者というのは、県研究所の人たち。
5ヶ所の中間育成場があり、4人の担当者がいます。
これまで、担当者間での意見交換が行われておらず、今年が初めての反省会です。
さて、マダイの中間育成で歩留まり(生き残り)が悪くなる原因は主に2つ。
病気 あるいは 餌
です。
特に餌が少ないと、共食いで歩留まりが悪化します。
病気であれば死んだ魚がいるのでわかりますが、共食いはわかりにくいのが難点です。
そして今回、餌でわかったことがあります。
指導担当者というのは、県研究所の人たち。
5ヶ所の中間育成場があり、4人の担当者がいます。
これまで、担当者間での意見交換が行われておらず、今年が初めての反省会です。
さて、マダイの中間育成で歩留まり(生き残り)が悪くなる原因は主に2つ。
病気 あるいは 餌
です。
特に餌が少ないと、共食いで歩留まりが悪化します。
病気であれば死んだ魚がいるのでわかりますが、共食いはわかりにくいのが難点です。
そして今回、餌でわかったことがあります。
放流方法の全般で
この計測方法、30年以上ずっと同じです。
でも、魚をカウントする方法も日々開発されているので、10年後は機械化されていると思います。
かなり「おおざっぱ」な放流尾数の把握ですが、だからと言ってやらないよりは全然マシ。
数字を残すことが大事です。
そして、海面での中間育成が漁師や漁協の減少で難しくなっています。
すでに神奈川県では中間育成を省略しています。
放流尾数のカウントだけでなく、放流方法も新技術が必要になっています。
でも、魚をカウントする方法も日々開発されているので、10年後は機械化されていると思います。
かなり「おおざっぱ」な放流尾数の把握ですが、だからと言ってやらないよりは全然マシ。
数字を残すことが大事です。
そして、海面での中間育成が漁師や漁協の減少で難しくなっています。
すでに神奈川県では中間育成を省略しています。
放流尾数のカウントだけでなく、放流方法も新技術が必要になっています。
放流尾数の計測
マダイの放流尾数は、一匹ずつ数えることが困難です。
やろうと思えばできます。
人がカチカチと、1分に100尾数えるとして、20万尾だと2000分。
33時間以上かかります。
4人なら8時間、8人なら4時間です。
休憩を入れると、この倍くらいの時間でしょうか。
この「1分に100尾」は熟練した人。
初めてだと、この何倍もかかります。
・・・だから、やろうと思いません。
そこで、魚の総重量を計測して、平均体重で割る方式を取ります。
これでも半日かかりますが、なんとかなります。
ここで問題になるのが、数字の信頼性。
魚の重量は、5kgくらいずつカゴに乗せ、アナログの台秤(だいばかり)で計測します。
カゴなので水は抜けますが、完全に抜けるのを待つと魚が死にます。
くわえて、水がなくなり魚があばれます。
秤の針がピタッととまることはありません。
これを、えいやっと読みます。「4.8キロ」とか。
この作業を1イケスで何十回もやって総重量が出ます。
今度は平均体重です。
約1キロの魚をバケツに移し、尾数を数えます。
この作業をイケスごとに「はじめ、中、終わり」の3回行います。
なぜ3回かと言えば、経験上、始めと終わりで平均体重が変わるからです。
それでも、3回の結果が近ければ良いのですが、ばらつきが大きいことも少なくありません。
こんな状況ですが、得られた総重量を平均体重で割ります。
ここで有効数字が登場。
最も低い有効数字(ケタ数)にあわせます。
このようなやり方では、どう見ても有効数字(信頼できる桁数)は2桁です。
万単位でしか信頼できそうな数字は得られません。
しかも、平均体重を計るときの1キロは、限りなく0.9キロと言った1桁に近い数字です。
せめて平均体重だけでも、魚を持ち帰って、精密に計れば有効数字2桁のなかでも正確になると思うんですけどね。
やろうと思えばできます。
人がカチカチと、1分に100尾数えるとして、20万尾だと2000分。
33時間以上かかります。
4人なら8時間、8人なら4時間です。
休憩を入れると、この倍くらいの時間でしょうか。
この「1分に100尾」は熟練した人。
初めてだと、この何倍もかかります。
・・・だから、やろうと思いません。
そこで、魚の総重量を計測して、平均体重で割る方式を取ります。
これでも半日かかりますが、なんとかなります。
ここで問題になるのが、数字の信頼性。
魚の重量は、5kgくらいずつカゴに乗せ、アナログの台秤(だいばかり)で計測します。
カゴなので水は抜けますが、完全に抜けるのを待つと魚が死にます。
くわえて、水がなくなり魚があばれます。
秤の針がピタッととまることはありません。
これを、えいやっと読みます。「4.8キロ」とか。
この作業を1イケスで何十回もやって総重量が出ます。
今度は平均体重です。
約1キロの魚をバケツに移し、尾数を数えます。
この作業をイケスごとに「はじめ、中、終わり」の3回行います。
なぜ3回かと言えば、経験上、始めと終わりで平均体重が変わるからです。
それでも、3回の結果が近ければ良いのですが、ばらつきが大きいことも少なくありません。
こんな状況ですが、得られた総重量を平均体重で割ります。
ここで有効数字が登場。
最も低い有効数字(ケタ数)にあわせます。
このようなやり方では、どう見ても有効数字(信頼できる桁数)は2桁です。
万単位でしか信頼できそうな数字は得られません。
しかも、平均体重を計るときの1キロは、限りなく0.9キロと言った1桁に近い数字です。
せめて平均体重だけでも、魚を持ち帰って、精密に計れば有効数字2桁のなかでも正確になると思うんですけどね。
稚魚放流体験イベントをお手伝い
7月21日にネッツトヨタ静岡さんが主宰する放流体験イベントに参加しました。
https://bokumachi.netz-shizuoka.net/save-cat/%ef%bc%97-23-%e7%9c%9f%e9%af%9b%e7%a8%9a%e9%ad%9a%e6%94%be%e6%b5%81%e8%a6%aa%e5%ad%90%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97
ネッツさんは放流協力金をいただいてる関係でのお手伝いです。
30分ほど栽培漁業の説明と、会場イケスで現場のご案内、マダイの体長測定などをやりました。
なかにはマダイを手でつかむのが苦手な子もいました。
女の子の方が元気だったかな。
小学校などで、栽培漁業に限らず水産の話をご希望の場合は、県庁に相談すると職員を派遣して出前授業をやってくれます。
もちろん、無料です。
https://bokumachi.netz-shizuoka.net/save-cat/%ef%bc%97-23-%e7%9c%9f%e9%af%9b%e7%a8%9a%e9%ad%9a%e6%94%be%e6%b5%81%e8%a6%aa%e5%ad%90%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97
ネッツさんは放流協力金をいただいてる関係でのお手伝いです。
30分ほど栽培漁業の説明と、会場イケスで現場のご案内、マダイの体長測定などをやりました。
なかにはマダイを手でつかむのが苦手な子もいました。
女の子の方が元気だったかな。
小学校などで、栽培漁業に限らず水産の話をご希望の場合は、県庁に相談すると職員を派遣して出前授業をやってくれます。
もちろん、無料です。
マダイの放流が終わりました
今年のマダイの放流が7月までに終了しました。
県内5カ所で中間育成を行っていますが、超高成績。
例年、中間育成の歩留まりは良くて7割くらいですが、3か所でほとんど10割の生き残りがありました。
厳密には10割ではありませんが、もはや測定誤差の範疇でした。
残念ながら2カ所は病気があって例年並みとなりました。
さて、この要因をこれから研究所の職員と分析です。
あきらかなのは、温水利用研究センター沼津分場で生産した種苗が素晴らしかったこと。
沖出しの時点で、そのできの良さは分かっていましたが、まさかここまでとは・・・
マダイの栽培漁業が始まって、何十年もたちますが、まだまだ技術が完成していないことの裏返しでしょうか?
県内5カ所で中間育成を行っていますが、超高成績。
例年、中間育成の歩留まりは良くて7割くらいですが、3か所でほとんど10割の生き残りがありました。
厳密には10割ではありませんが、もはや測定誤差の範疇でした。
残念ながら2カ所は病気があって例年並みとなりました。
さて、この要因をこれから研究所の職員と分析です。
あきらかなのは、温水利用研究センター沼津分場で生産した種苗が素晴らしかったこと。
沖出しの時点で、そのできの良さは分かっていましたが、まさかここまでとは・・・
マダイの栽培漁業が始まって、何十年もたちますが、まだまだ技術が完成していないことの裏返しでしょうか?
令和5年6月
2023-06-20
沖出し終了!
昨日までに県内三カ所でのマダイの沖出しが終了しました。
台風による日程変更があったものの、それ以外は順調に推移。
特に温水利用研究センターの沼津分場では高品質の種苗を作ってくれました。
種苗生産にマニュアルはあるものの、未だに担当者の技量によるところが大きいのが現実です。
海水を使っているため、海の状況にも左右されます。
悲しいですがマダイに限っても、技術が完成されているとは言えない状況です。
台風による日程変更があったものの、それ以外は順調に推移。
特に温水利用研究センターの沼津分場では高品質の種苗を作ってくれました。
種苗生産にマニュアルはあるものの、未だに担当者の技量によるところが大きいのが現実です。
海水を使っているため、海の状況にも左右されます。
悲しいですがマダイに限っても、技術が完成されているとは言えない状況です。
いやいや・・・
ごめんなさい。
5月は1回しか更新しませんでした・・・
さて今週からマダイの沖出しが始まっています。
明日も沼津で沖出しの予定でしたが天候不良で来週になってしまいました。
私が引き継いでから、初めての順延です。
今日の午前中は、その調整でワラワラでした。
ところで、マダイが放流されたものであるかを鼻孔隔皮欠損という、鼻の穴の状態で見分けます。
https://fish-exp.pref.shizuoka.jp/izu/0006/341/341-10.pdf
なぜ、天然のマダイと人工種苗で違いがあるのか???と言うのは良く分かっていません。
私が想像するに、人工種苗は餌の豊富な環境でグングン成長します。
そのため、急激に大きくなるために天然魚と体のつくりが細かいところで異なってしまうことが原因では?と思っています。
成長を遅くすれば確認できるんですけどね。
ただし、マダイは十分に餌をやらないと、共食いでどんどん減るので、事業規模では確認が難しいところです。
鼻孔隔皮欠損になる理由をご存じの方は教えて下さい。
5月は1回しか更新しませんでした・・・
さて今週からマダイの沖出しが始まっています。
明日も沼津で沖出しの予定でしたが天候不良で来週になってしまいました。
私が引き継いでから、初めての順延です。
今日の午前中は、その調整でワラワラでした。
ところで、マダイが放流されたものであるかを鼻孔隔皮欠損という、鼻の穴の状態で見分けます。
https://fish-exp.pref.shizuoka.jp/izu/0006/341/341-10.pdf
なぜ、天然のマダイと人工種苗で違いがあるのか???と言うのは良く分かっていません。
私が想像するに、人工種苗は餌の豊富な環境でグングン成長します。
そのため、急激に大きくなるために天然魚と体のつくりが細かいところで異なってしまうことが原因では?と思っています。
成長を遅くすれば確認できるんですけどね。
ただし、マダイは十分に餌をやらないと、共食いでどんどん減るので、事業規模では確認が難しいところです。
鼻孔隔皮欠損になる理由をご存じの方は教えて下さい。
| もっと見る |